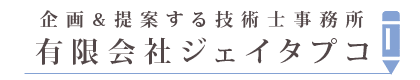ここ数年,日本では,技術分野において,データの改ざんなどの不正行為が立て続けに明らかになっています。
*杭打ちデータの改ざん
*地盤改良工事で施工データの改ざん(こちら)
*免震装置の性能のデータの改ざん
*自動車の燃費の改ざん
*無資格者による車の完成検査
*製鉄会社の製品のデータの改ざん
昨日も,「非鉄大手の会社の子会社で品質データの改ざんがあった」との報道がありました。
これらの不正を犯す原因の1つに「ノルマ」があると思います。
無資格者による車の完成検査を伝えたテレビのニュースや新聞記事の中にも,この不正行為の背景には,会社から課せられたノルマがあったと伝えたところもありました。
「これだけの車の検査をして,これだけの数を出荷しなさい。ただし,検査員の数はこれだけ,人件費はこれだけの範囲で行いなさい。期限は○○までです」というノルマが課せられたら,現場で働く社員には,相当なプレッシャーがかかると思います。

このままでは、ノルマが達成できないとわかったとき,「なんとかしなくちゃ」と思い,例えば,無資格者による車の完成検査を行うのではないでしょうか。
“ノルマが課せられる”
という言葉を使いましたが,実際に今,会社からノルマが課せられている方も多いと思います。
ちなみに,ノルマを辞典(岩波 国語辞典 第5版)で調べると,以下の意味が書かれています。
「基準。特に,各個人・工場等に割り当てられた,労働の基準量。」
余談ですが,「ノルマ」には強制的な響きがあります。あまり良いイメージの言葉ではありません。「ノルマ=労役」のように思います。
ノルマと同じような意味に「目標」があります。しかし,「ノルマと目標」では,これらを読んだときの感じ方が違います。「ノルマ」はネガティブなイメージですが,「目標」は自発的でポジティブなイメージがあります。
会社からのノルマが達成できそうにもないとわかったとき,「『不正を犯してでも会社からのノルマを達成しよう』という考え」と「技術者の倫理」が対立します。
日本機械学会倫理規定の綱領の1では,以下のようなことが書かれています。なお,アンダーラインは弊社で付けました。
1.技術者としての社会的責任
会員は,技術者としての専門職が,技術的能力と良識に対する社会の信頼と負託の上に成り立つことを認識し,社会が真に必要とする技術の実用化と研究に努めると共に,製品,技術および知的生産物に関して,その品質,信頼性,安全性,および環境保全に対する責任を有する。また,職務遂行においては常に公衆の安全,健康,福祉を最優先させる。
この日本機械学会倫理規定を参考にするならば,「『不正を犯してでも会社からのノルマを達成しよう』という考え」と「アンダーラインの箇所」が対立します。
不正を犯す場合には,「不正を犯してでも会社からのノルマを達成しよう」という考えが勝ちます。
ただ,不正を犯す場合でも,「この程度の不正ならば製品の安全に問題ないだろう」という考えがあると思います。「不正を犯せば,製品の安全が確保できない」とわかっている場合には,不正を犯さないと思いますが・・・。
今後も,様々な技術分野で,「会社から課せられたノルマ」と「技術者の倫理」とが対立するでしょう。
このブログを読まれた技術者の方は,どちらを選びますか?