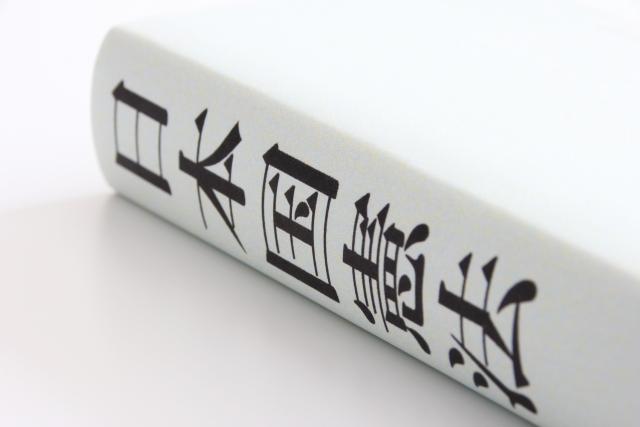今月初めに,「経済協力開発機構(OECD)による15歳を対象とした国際学習到達度調査(PISA)で日本の読解力が前回(2015年実施)の8位から15位に急落した」というニュースをテレビで見ました。日本からは全国約6,100人の高校1年生がテストを受けたそうです。
このニュースについて書かれた新聞が先日出てきたので読んでみました。この記事の中に以下のことが書かれていました。
・・・調査では,本や新聞をよく読む生徒の方が読解力の得点が高い結果が出た。一方で新聞を「月に数回」「週に数回」読むと答えた日本の生徒は21.5%で,約10年前に比べて36ポイントも減った。・・・
読解とは,「文章を読んでその意味を理解すること。文章の意味を読み取ること(岩波国語辞典第5版)」です。読解力とはこの能力のことです。
この読解(読解力)の定義から,「本や新聞をよく読む生徒の方が読解力の得点が高い結果が出た」ことは当たり前の結果だと思います。
新聞を「月に数回」「週に数回」読むと答えた生徒の割引が減少した理由の1つとしてスマートフォンの普及があると思います。

本を読むことは読解力をレベルアップさせると思います。
「自省録」という本があります(こちら)。この本は,ローマの皇帝のマルクス・アウレリウスが書いた哲学書です。このマルクス・アウレリウスは五賢帝の一人です。
この本を読んだとき,1回読んだだけでは内容(マルクス・アウレリウスの考え)が頭の中にしっかり入りませんでした。しかし,何度も読み返すとマルクス・アウレリウスの考えが頭の中に入ってきました。
本を読むことで読解力が向上するのは,このように著者の考えなどを文章から読み取るからだと思います。
もちろん,何度も読み返さなくても著者の考えなどが頭の中にスッと入る本もありますが・・・・。
読解力は,児童・生徒・学生などだけではなく大人にも求められる能力です。グーグルで「読解力 本」と入力して検索すると数多くの本が出てきます。
検索結果の中で過去に読んだ本も出てきました。
「わかったつもり 読解力がつかない本当の原因:西村克彦(光文社新書)」です。2017年8月8日に掲載したブログでこの本を紹介しました(こちら)。
最近,本をじっくりと読む時間が取れませんが,この新聞記事を読んで,「自分の読解力をレベルアップさせるためにも時間をつくって読書をしよう」と思いました。